

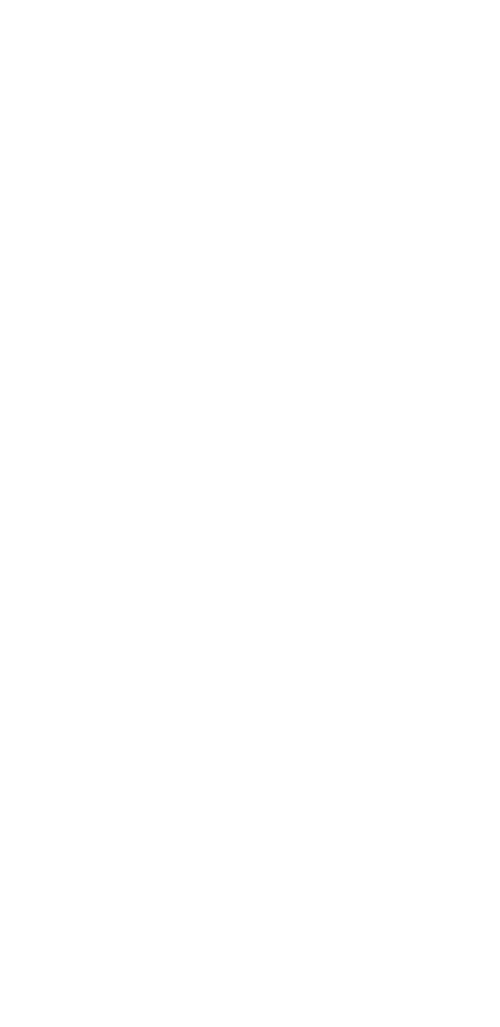



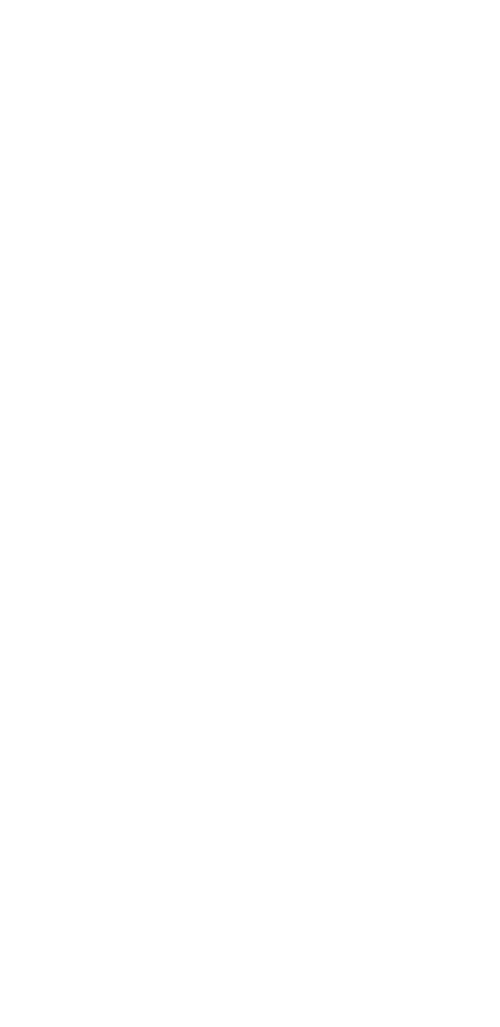



追悼平和祈念館では、原子爆弾による被害の実相を広く国の内外に伝え、永く後代まで語り継ぐために、様々な事業に取り組んでいます。被爆76年が経過し、「被爆者が語れなくなる時代」が近づくにつれて、被爆の実相を伝えることが年々難しくなっています。そのような中で制作された映画「祈り」は、原爆の惨禍を映像として、その後も苦しみ続けた被爆者の無念さや想いを伝えています。「長崎を最後の被爆地に!」するため、「原子雲の下で何が起こったか」を知ってください。ナガサキを知ることは、自分たちの未来を考えることです。
戦争、そして原爆は、物や肉体ばかりでなく、多くの人の“心”を深く傷つけました。この、長崎原爆を描いた異色の映画の登場人物たちはみな、心に大きな傷を持ちながらも、自らの信仰に生き、神に祈りつつ人事を尽くしながら、時代を懸命に生きています。
昨秋、試写会で本編を観賞したときに覚えた震えは、川棚での晩冬のロケを想起したからではありません。決して繰り返すことがあってはいけない時代。そのためにも、我々ひとりひとりができることを、実践するときが今、来ています。
「祈り」、それは行動です。
戦争の影をひきずった物語が語られることは少なくなった。「祈り─幻に長崎を想う刻─」になにかなつかしさを感じたのはそのせいだろうか。
戦争の影を背負い、戦後の復興からも取り残された人々──、信仰に生きる被爆者や、娼婦、やくざといった市井の人々が、この映画ではともにぐつぐつと煮えたぎってもがいている。
かれらは復興と繁栄にまっすぐに走りだすことを、どこかでためらっているようにも感じる。廃墟を撤去してしまったらなにかを失ってしまうのではないか。
戦後を生きるとは、そのような「ためらい」を生きることだったのかもしれない。 「祈り─幻に長崎を想う刻─」は私たちが見失った戦後をあらためて問いかけてくる。
映画の舞台となる昭和32年は国の被爆者援護が始まった年です。
まちの形は復興を遂げたかのように見えますが、多くの被爆者は心と体に深い傷を負い、貧困や差別に苦しんでいたことを、改めて痛感しました。
この映画を通して当時の人々の心情に触れ、被爆の実相をより深く知ってもらうきっかけになれば、と思います。
- Comments -